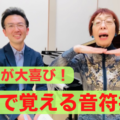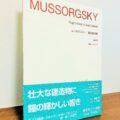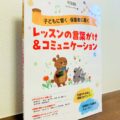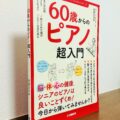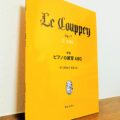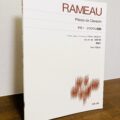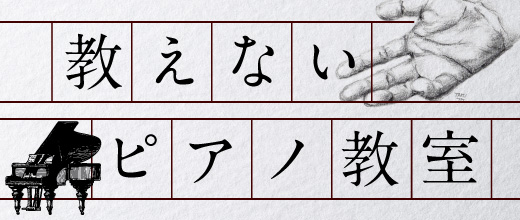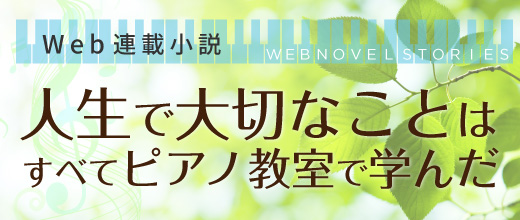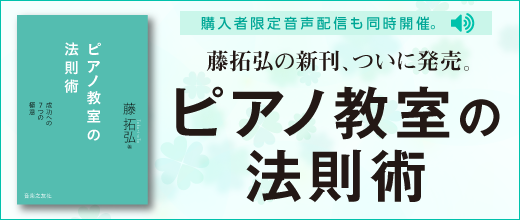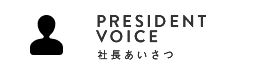YouTubeピアノ講師ラボチャンネルの対談シリーズ第6弾は、田村智子先生がご登場!
2023年4月4日UP! ピアノ講師ラボ
「ピアノ講師ラボ」のYouTubeチャンネル。 おかげさまで、開始から3か月ほどで、 チャンネル登録者数も1,330名を超えてきました。 いつもご覧いただき、本当にありがとうございます。 さて、4月に入ったこともあり、 …
発表会の選曲で役立つ珠玉の作品を集めたピアノ曲集「弾きたい曲がいっぱい!ピアノのたからばこ ターコイズ」(音楽之友社・編)
2023年3月31日UP! ピアノ教本・曲集
おはようございます。 株式会社リーラムジカ代表取締役の藤 拓弘です。 今日ご紹介するのは、 「ピアノのたからばこ ターコイズ」 という曲集です。 発表会やレッスンで使えるような ピアノ曲集をいつも探している。 そんなピア …
なかなか触れることのない日本人作曲家によるピアノ作品「日本の小品集 New Edition」花岡千春・校訂、運指、解説(音楽之友社)
2023年3月24日UP! ピアノ教本・曲集
おはようございます。 株式会社リーラムジカ代表取締役の藤 拓弘です。 今日ご紹介するのは、 「日本の小品集 New Edition」 という楽譜です。 ピアノの作品というと、主に欧米の作曲家に フォーカスされることが多い …
小さな手のことも考慮された音楽的な運指など実用的な楽譜「ムソルグスキー 展覧会の絵 New Edition」西尾洋・解説、朴久玲・運指(音楽之友社)
2023年3月16日UP! ピアノ教本・曲集
おはようございます。 株式会社リーラムジカ代表取締役の藤 拓弘です。 今日ご紹介するのは、 「ムソルグスキー 展覧会の絵 New Edition」 という楽譜です。 「展覧会の絵」といえば、ラヴェル編曲の 管弦楽版を思い …
幅広い執筆陣によるコミュニケーションについての話題が満載「レッスンの言葉がけ&コミュニケーション」ONTOMO MOOK ムジカノーヴァ・編(音楽之友社)
2023年3月9日UP! ピアノ教本・曲集
おはようございます。 株式会社リーラムジカ代表取締役の藤 拓弘です。 今日ご紹介するのは、 「レッスンの言葉がけ&コミュニケーション」 というムック本です。 ピアノのレッスンで大切なのが、 お子さまとのコミュニケーション …
シニアの方のピアノライフの第一歩目をサポートする教材「60歳からのピアノ超入門」元吉ひろみ・著(ヤマハ)
2023年3月1日UP! ピアノ教本・曲集
おはようございます。 株式会社リーラムジカ代表取締役の藤 拓弘です。 今日ご紹介するのは、 「60歳からのピアノ超入門」 という教材です。 最近では、シニアの方を対象として、 レッスンを展開される先生も増えましたね。 ピ …
豊富な執筆陣が幼児のレッスンで活かせるアイデアを紹介「プレ・ピアノレッスンのアイディア集」ONTOMO MOOK ムジカノーヴァ・編(音楽之友社)
2023年2月22日UP! ピアノ教本・曲集
おはようございます。 株式会社リーラムジカ代表取締役の藤 拓弘です。 今日ご紹介するのは、 「幼児の心をつかむ プレ・ピアノレッスンのアイディア集」 というムック本です。 ピアノ指導において最も大切な、 導入期でのレッス …
最初のレッスンにどこまでもこだわるべき理由「ピアニストの関本昌平先生が語る!自然に美しい表現ができる生徒を育てるピアノ指導の極意(前編)」【ピアノ講師ラボ】2023年3月号
2023年2月19日UP! ピアノ講師ラボ
来月2023年3月号の「ピアノ講師ラボ」に ご登場はピアニストの関本昌平先生。 関本昌平先生といえば、皆さまご存じ、 第15回ショパン国際コンクールで第4位という、 素晴らしいご経歴の世界的なピアニストです。 現在は、演 …
ピアノで弾きながら体感的に和声を身に付けられる復刻教材「新版 たのしいこどものけんばんわせい」村川千秋・著、中田喜直・監修(音楽之友社)
2023年2月14日UP! ピアノ教本・曲集
おはようございます。 株式会社リーラムジカ代表取締役の藤 拓弘です。 今日ご紹介するのは、 「新版 たのしいこどものけんばんわせい」 という教材です。 ピアノ学習者にとって、 和声の知識はとても大切です。 大切だからこそ …
安川加壽子先生が校訂の70年以上のロングセラー練習曲集「ル・クーペ 新版 ピアノの練習ABC」安川加壽子・校訂・註(音楽之友社)
2023年2月8日UP! ピアノ教本・曲集
おはようございます。 株式会社リーラムジカ代表取締役の藤 拓弘です。 今日ご紹介するのは、 「ル・クーペ 新版 ピアノの練習ABC」 という教材です。 昔から愛されている教本や教材は、 ピアノ教育業界にはたくさんあります …